雑損控除とは

雑損控除とは、地震や水害の自然災害・火災の人的災害に加え・盗難や横領などに遭った場合に発生した資産の損失を、その年の所得から差し引くことができます。
対象となる損失は、生活にかかる住宅や家財などの財産であり、趣味に使用するものや高額な貴金属・骨董品などは除外されます。
これらの損失については、本人および生計を共にする家族に対しても適用され、確定申告を行うことで所得からの控除が可能です。
生活にかかる部分にのみ適用されるもので、事業用の固定資産や棚卸資産といった資産は対象外です。
損害とみなされる状態
①自然災害…地震や水害に加え、風害・雪害・落雷のように、自然現象により起こりうる様々な災害を指します。これらの災害の復旧、もしくは防止のために使用した備品の購入費用も含まれます。
②人的災害…火災や爆発など人為的な事象から起きた災害の中で、予期できず被害の程度が異常な場合は対象になります。
③盗難…生活に必要である家財などが盗難にあった場合が対象になります。財産の損失について明らかな盗難と判断できない場合、損失したタイミングが測れない場合では、紛失とみなされ対象外になります。
④横領…金銭の管理を任せている第三者に金品を横領された場合は、法律における判断によって適用されます。経営者が従業員に管理を委任していることが証明できる場合に限ります。
⑤害虫・害獣による損失…シロアリの害虫やイノシシの害獣などによって、居住用の建物に重大な被害を受けた場合は対象になります。
雑損控除を受けられる条件
雑損控除は、生活にかかる住宅や家財すべてに適用されるわけではなく控除を受ける人について条件を満たしていることが必要です。
①所得税を支払う本人が所有するものであること
②納税者と生計を共にする家族が所有するもので、家族の総所得金額が48万円以下であること
雑損控除に含まれないもの
①自分の意思で財産を譲渡した詐欺もしくは恐喝などによる損失
②事業用資産
③別荘や貴金属・骨董品のように生活の域を超えた趣味や娯楽のうち個別の価格が30万円を超えるもの
④住宅といった生活に必要な財産の修復の際に原状回復以上の価値や機能を付け加えた部分
損害にかかる費用の範囲
①保険金以外で、損失に対して支払った各種費用
②住宅などの解体や撤去にかかった費用
③災害が落ち着いてから1年以内に原状回復のために供した費用
④被害の拡大および再発を防ぐための対策費用
⑤盗難、横領にかかる損害を原状回復するための費用

基本的には、損失から原状回復するまで、またさらなる災害を防止するための費用が雑損控除として認められています。
雑損控除の計算方法
損失を受けた金額について、明確でない場合には基本的にその財産の時価を鑑みて計算を行います。
住宅の場合は柱や床・屋根といった主要構造部に損失を受けた時のみ算出が可能です。
住宅が全壊した場合、損失額は100%で算出することができます。
時価判断できない場合や、半壊・部分的な損害の場合は損害がいくらになるのかは計算が難しいです。
そのような場合は、下記の計算方法で計算します。
①取得価額がはっきりしている時の計算式…(財産の取得価額-減価償却費)×被害割合
②取得価額がはっきりとわからない時の計算式
《住宅》〔(1平方メートルあたりの工事費用×住宅の総床面積)-減価償却費〕×被害割合
《家財》家族構成別家庭用財産評価額×被害割合(家族構成別家庭用財産評価額とは、世帯主の年齢や家族の人数に応じて家財の価値を概算するもの)
難しいので、国税庁の公式リンクを貼っておきますね。
差引損失額の計算
雑損控除の金額を計算するために用いる差引損失額を計算します。
損失額+損失にかかる最低限の支出額(修繕費など)-保険金・損害賠償金などの補てん金=差引損失額
①差引損失額-総所得金額×10%
②差引損失額のうち、災害にかかる支出額-5万円
①か②のいずれか多いほうが雑損控除額になります。
雑損控除額の計算
差引損失額の計算…損失額50万円、災害にかかる支出30万円、保険金による補てん分10万円とする
50万円+30万円-10万円=70万円
雑損控除額の計算…所得税を納める本人の総所得金額を300万円とし、雑損控除額の2種類の計算方法で計算します。
①70万円-300万円×10%=40万円
②30万円-5万円=25万円
①のほうが金額が多いため、雑損控除額は40万円となります。
雑損控除額が所得金額を超える場合
雑損控除が適用される条件を満たし、その金額を所得から差引いて赤字になった場合、赤字部分は雑損失とみなされます。
この場合、翌年以降3年間にわたり所得と相殺(損益通算)する「雑損失の繰越控除」が利用できます。
もし赤字が出た場合は、この3年間のうち赤字額が相殺できるまで確定申告を行う必要があります。
災害減免法
生活にかかる財産の時価の2分の1以上を災害により損失した場合、災害減免法の適用を受けることができます。
災害減免法はその年の総所得額1,000万円以下の人にのみ適用されます。
災害減免法は災害での損失のみが対象です。
災害減免法は対象物の時価の2分の1以上の損失を受けていることが条件です。
災害減免法は確定申告で所得税額そのものを軽減します。
総所得額の合計500万円以下…軽減・免除される所得税額は全額
総所得額の合計500万円超~750万円以下…軽減・免除される所得税額は所得税額の2分の1
総所得額の合計750万円超~1,000万円以下…軽減・免除される所得税額は所得税額の4分の1
用意する書類
①確定申告書…会社員などで雑損控除・災害減免法のみを申告する場合は確定申告書Aを使用します。
②り災証明書…災害による損失を受けた場合、その被害について証明される書類です。発行は、災害であれば自治体、盗難であれば警察で受けることができます。
③被害を受けた建物の詳細…建物が損失被害を受けた時は登記簿謄本や固定資産税明細書、土地所有者や取得価額の詳細がわかる書類を用意します。
④被害を受けた家財・車両などの詳細…家財や車両が被害に遭った場合は、取得価額や購入時期がわかる領収書もしくは契約書類などを用意します。
⑤修繕費などの明細…被害を受けた財産について、取壊しや撤去・修理を含む修繕費の支出が発生した場合は工事の見積書や領収書を用意します。
➅補助金を受けた場合は、その金額を証明するもの…保険金や補助金で補てんを受けた場合は、その金額が証明できる銀行口座通帳のコピーや支払通知書を用意します。
確定申告書の書き方
雑損控除の場合
雑損控除の申告の場合、確定申告書第一表に雑損控除欄があるため、算出した金額を記入します。
第二表の雑損控除欄には、
①損害の原因
②損害年月日
③損害を受けた資産の種類
④損害金額
⑤保険金棟で補てんされる金額
➅差引損失額のうち、災害関連支出の金額
災害減免法の場合
災害減免法の申告を行う場合、確定申告書第一表における所得金額の計算で所得の計算を行います。
その所得額を前述の災害減免法の割合に当てはめ、第一表の税金の計算欄内の災害減免額に該当額を記入します。
まとめ
雑損控除は、生活にかかる財産の損失について控除を受けることができます。
災害減免法は、所得税を圧縮する方法することができます。
いずれかを選ぶことができるため、それぞれに計算して適切な方法を選びましょう。

ここがポイント‼
《少し難しいようでしたら、お近くの税務署に相談するのがいいと思います。》
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
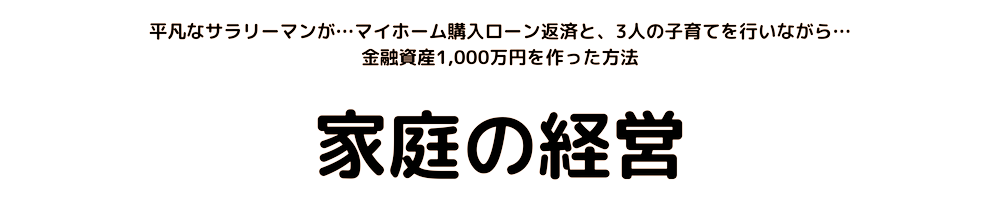

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c6787b5.ff03140f.2c6787b6.376aa2ac/?me_id=1213310&item_id=21432338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3780%2F9784023323780_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント